
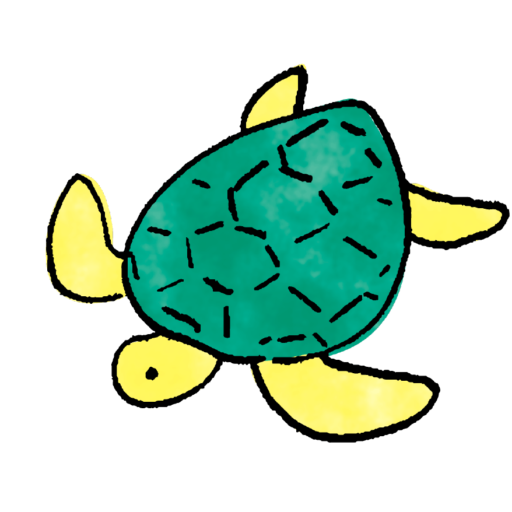
世界的にも注目されているブルーカーボン。日本ではどんな取り組みがされているんだろう?
日本におけるブルーカーボンの取り組みは、海洋や海岸域の生態系を活用して二酸化炭素の吸収や貯留を促進し、地球温暖化対策や持続可能な開発に貢献することを目指しています。以下に、日本でのブルーカーボンに関する具体的な取り組みを紹介します。
マングローブや海草の保護と再生
日本では、マングローブや海草などの海洋生態系の保護と再生が進められています。
これらの生態系は、二酸化炭素を吸収し、貯留する能力が高く、海洋環境の保全と同時にブルーカーボンの利活用にもつながります。例えば、マングローブ林の再生プロジェクトや海草の保護活動が行われています。


参考:ブルーカーボンに関する取り組み|環境省
CO2吸収量の評価とモニタリング
日本では、海洋や海岸域におけるCO2吸収量やブルーカーボンの量を評価し、モニタリングする取り組みが進められています。海洋観測船や衛星データを活用して、海洋生態系のCO2吸収量や炭素貯留量を定量化し、研究や政策立案に活用しています。
参考:宇宙から海へ:ブルーカーボンのプロジェクトにおける衛星データの重要性
炭素貯留技術の研究開発
日本では、炭素貯留(ちょりゅう)技術の研究開発が進められています。海洋や海岸域における炭素貯留のための新たな技術や施設の開発が行われ、地球温暖化対策や持続可能な開発に貢献することが期待されています。例えば、海底埋設型CO2貯留技術や海洋堆積物(たいせきぶつ)の利活用技術が研究されています。
経済産業省で技術の開発を支援
CCS
「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留」技術と呼ばれます。発電所や化学工場などから排出されたCO2を、ほかの気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入するというものです。
CCUS
「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略で、分離・貯留したCO2を利用しようというものです。
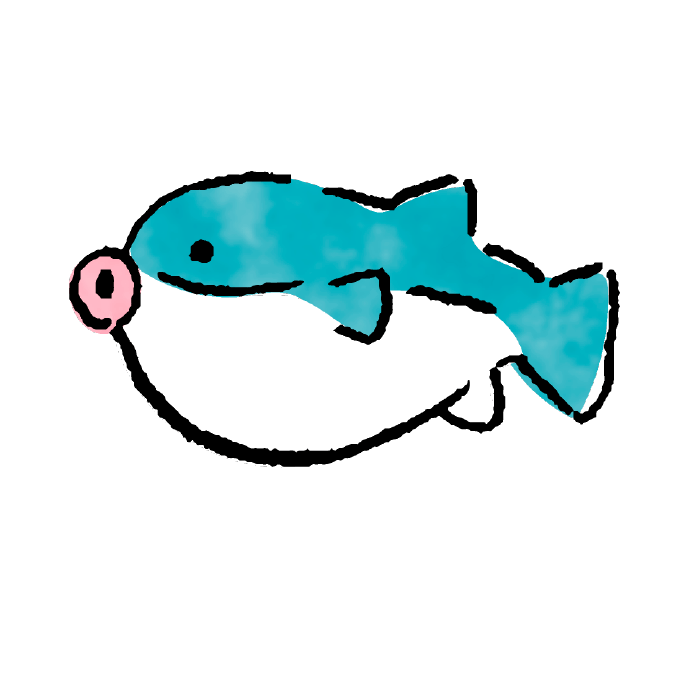
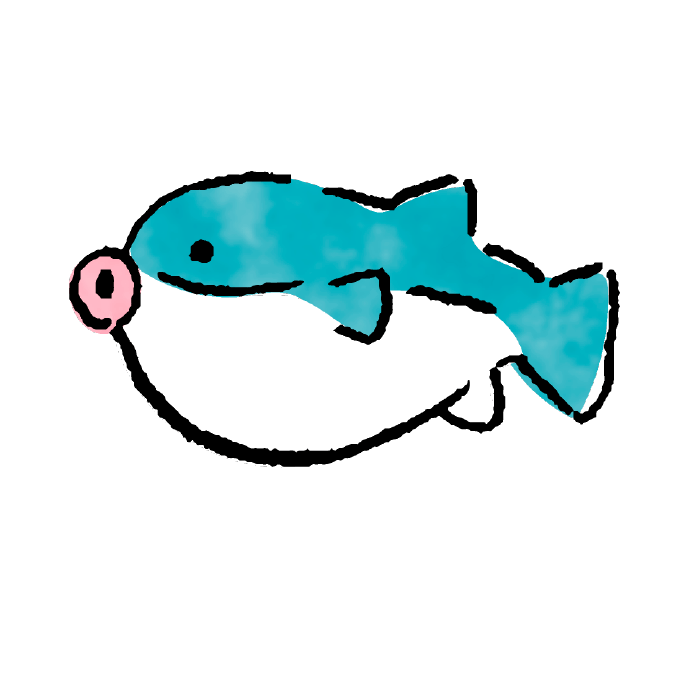
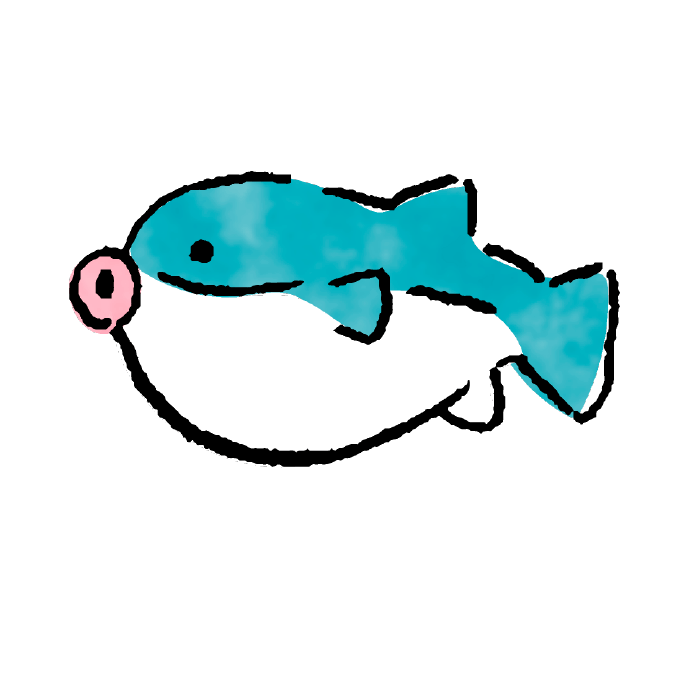
周りを海に囲まれている島国の日本だからこそ、できる取り組みがあるんだね!
国際協力と政策立案
日本は国際社会との協力を通じて、ブルーカーボンの問題に取り組んでいます。国際連合などの国際機関や国際協力機構を通じて、技術移転やノウハウの共有、政策立案などが行われ、地球規模でのブルーカーボンの利活用が推進されています。
意識啓発と教育活動
日本では、ブルーカーボンに関する意識啓発や教育活動が行われています。学校教育や市民向けのイベント、啓発キャンペーンなどを通じて、ブルーカーボンの重要性や地球環境への貢献度を広く啓発し、社会全体での取り組みを促進しています。
以上のように、日本では海洋や海岸域の生態系を活用したブルーカーボンの取り組みが進められています。
これらの取り組みは、地球温暖化対策や持続可能な開発において重要な役割を果たし、地球環境の保全と人々の生活向上に貢献しています。
